「子供がフェンシングに興味を持った!ぜひやらせてあげたい!」 「テレビで見てカッコよかった。うちの子にも体験させたいな」
華麗な剣さばき、騎士道精神に通じる礼儀作法、そして「考えるスポーツ」とも言われる戦略性。フェンシングは、お子様の心身の成長に多くのメリットをもたらす魅力的なスポーツです。しかし、その一方で、多くの保護者の方が最初に気になるのが費用の問題ではないでしょうか?
「フェンシングって、なんだかお金がかかりそう…」 「特に、あのマスクとか剣とか、用具一式揃えるのにいくらかかるの?」 「もしすぐに飽きちゃったら、初期費用が無駄になるかも…」
そんな不安を感じて、一歩踏み出すのをためらっていませんか?
ご安心ください!確かにフェンシングの用具は決して安価ではありませんが、初期費用を賢く抑える方法はいくつもあります。
この記事では、フェンシングを始める際に具体的にどのような費用が、いくらくらいかかるのか、そして、その負担を少しでも軽くするための5つの具体的な節約術を、フェンシング経験者かつ熱心な保護者としての視点から徹底解説します。
この記事を読めば、フェンシングの初期費用に関する漠然とした不安が解消され、お子様の「やってみたい!」という気持ちを前向きに応援できるようになるはずです。
フェンシング開始時に必要な初期費用:内訳と相場を大公開!
まず、フェンシングを始めるにあたって、具体的にどのような費用がかかるのかを見ていきましょう。大きく分けて、「クラブ関連費用」と「用具費用」があります。
1. クラブ関連費用
これらは所属するクラブによって大きく異なりますが、一般的には以下のものが考えられます。
- 入会金: 5,000円~15,000円程度が相場ですが、クラブによっては不要な場合もあります。
- 月謝(または年会費): 週の練習回数や時間、施設の充実度、コーチの経歴などによって様々です。小学生の場合、月額5,000円~15,000円程度が多いようです。年会費制のクラブもあります。
- スポーツ安全保険料: 年間1,000円~2,000円程度。万が一の怪我に備えて加入が義務付けられていることがほとんどです。
ポイント: クラブを選ぶ際には、月謝だけでなく、入会金やその他の費用(施設利用料など)も事前にしっかり確認しましょう。体験入会などを利用して、クラブの雰囲気や指導方針が子供に合っているかも見極めることが大切です。
2. 用具費用
ここが最も気になる部分かと思います。フェンシングは安全確保のため、専用の用具を揃える必要があります。主に必要なものは以下の通りです。(種目:フルーレ、エペ、サーブルによって剣や一部用具が異なりますが、ここでは一般的なものを挙げます)
| 用具の種類 | 役割・特徴 | 相場(初心者向け・子供用) |
|---|---|---|
| マスク | 顔面を保護する最も重要な防具。頭部全体を覆う。 | 15,000円 ~ 30,000円 |
| ジャケット | 上半身を保護する厚手の白いユニフォーム。 | 15,000円 ~ 30,000円 |
| プラストロン(半プロ) | ジャケットの下に着る、利き腕側の胸部を保護するプロテクター。 | 5,000円 ~ 10,000円 |
| グローブ | 剣を持つ手を保護する手袋。 | 3,000円 ~ 7,000円 |
| パンツ | 膝下までを保護する白いユニフォーム。 | 10,000円 ~ 20,000円 |
| ソックス | 膝下まである厚手の専用ソックス。 | 2,000円 ~ 4,000円 |
| シューズ | 専用シューズが望ましいが、体育館シューズでも可の場合も。 | 5,000円 ~ 15,000円 |
| 剣(ブレード) | 種目により形状、重さが異なる。最初は練習用から。 | 5,000円 ~ 15,000円 |
| ボディコード | 電気審判機を使用する場合に、剣とリールを繋ぐコード。 | 3,000円 ~ 6,000円 |
| マスクコード | 電気審判機を使用する場合に、マスクとメタルジャケット(種目による)を繋ぐコード。 | 2,000円 ~ 4,000円 |
| バッグ | 長い剣や用具一式を収納・運搬するための専用バッグ。 | 8,000円 ~ 20,000円 |
| 合計(目安) | 約73,000円 ~ 161,000円 |
※注意:
- 上記はあくまで目安であり、メーカーや品質、購入場所によって価格は変動します。
- 電気審判機を使用しないクラブや、最初は不要な用具もあります(ボディコード、マスクコードなど)。クラブに確認しましょう。
- 種目(フルーレ・エペ・サーブル)によって必要なメタルジャケットなどが加わると、さらに費用がかかります。
正直、「やっぱり高い!」と思われたかもしれません。 特にマスクやジャケットは高価です。しかし、これらの用具はお子様の安全を守るために不可欠なものです。だからこそ、次のセクションで紹介する「節約術」が重要になってきます。
高価なフェンシング用具代を賢く抑える!今日からできる5つの節約術
合計で10万円前後、あるいはそれ以上かかる可能性のある初期費用。これを少しでも抑えるための具体的な方法を5つご紹介します。
節約術①:中古品・お下がりを積極的に活用しよう
最も効果的な節約術の一つが、中古品やお下がりを利用することです。
- 入手方法:
- クラブの先輩や卒業生: クラブ内で不要になった用具を譲ってもらえないか、コーチや他の保護者に相談してみましょう。良い関係性が築けていれば、快く譲ってくれたり、安価で販売してくれたりすることがあります。
- フリマアプリ・ネットオークション: 「メルカリ」「ラクマ」「ヤフオク」などで「フェンシング 用具 子供」「フェンシング マスク 中古」などと検索すると、出品されていることがあります。
- **フェンシング専門の中古販売:**数は少ないですが、中古用具を扱う専門店やオンラインショップが存在する場合もあります。
- メリット: 新品を購入するより大幅に費用を抑えられます。 成長期ですぐにサイズアウトしてしまう可能性を考えると、非常に有効な手段です。
- 注意点:
- 安全性: 特にマスクは重要です。へこみやメッシュの歪み、内部パッドの劣化がないか、安全基準(FIEマークの有無など。後述)を満たしているかなどをしっかり確認しましょう。不明な場合は経験者やコーチに見てもらうのが安心です。
- 状態: 汚れや破れ、消耗度合いを確認しましょう。写真は加工されている可能性もあるため、可能であれば実物を確認するか、出品者に詳細な状態を問い合わせましょう。
- サイズ: 子供の体に合っているかどうかが重要です。試着できない場合は、出品されているサイズ表記をよく確認し、現在の身長や体型と照らし合わせましょう。
- 衛生面: 中古品は必ず洗濯や消毒を行い、清潔な状態で使用しましょう。
節約術②:クラブのレンタル制度を確認してみる
クラブによっては、初心者向けに用具のレンタル制度を設けている場合があります。
- 確認事項:
- レンタル可能な用具の種類(マスク、剣だけ?一式?)。
- レンタル料金(月額、年額など)。
- レンタル期間。
- 破損・紛失した場合の規定。
- メリット:
- 初期費用を劇的に抑えられます。 まずはレンタルで試してみて、子供が本当にフェンシングを続けたいかを見極めることができます。
- サイズが変わっても交換してもらえる場合があります。
- メンテナンスの手間がかからない場合もあります。
- デメリット:
- 長期的に見ると、購入するより割高になる可能性があります。
- 選べる用具の種類やサイズが限られている場合があります。
- 常に「借り物」であるため、自分のものとして大切に扱う意識が薄れる可能性も(もちろん、レンタル品も丁寧に扱うべきですが)。
- そもそもレンタル制度がないクラブも多いです。
まずは所属を検討しているクラブに、レンタル制度の有無と詳細を確認してみましょう。
節約術③:コスパ良し!初心者向けセット商品を検討する
フェンシング用品メーカーや専門店では、初心者に必要な用具を一式まとめた「初心者セット」や「スターターキット」を販売していることがあります。
- メリット:
- 個別に揃えるよりも割安な価格設定になっていることが多いです。
- 何を買えば良いか分からない初心者にとって、必要なものが一通り揃っているので手間が省けます。
- セット内容は初心者向けに選ばれているため、大きな失敗が少ないです。
- デメリット:
- セット内容が固定されているため、特定のメーカーやデザインにこだわりたい場合には向きません。
- セットに含まれる用具のグレードは、基本的にエントリーレベルのものです(初心者のうちは十分ですが)。
- 選び方のポイント:
- セット内容をよく確認し、本当に必要なものが含まれているかチェックしましょう(ボディコードなどは後から買い足せる場合も)。
- 安全基準(FIEマークの有無など)を確認しましょう。
- 可能であれば、試着してサイズを確認できるとベストです。
オンラインストアや専門店で、「フェンシング 初心者 セット」などのキーワードで探してみましょう。
節約術④:セール時期や型落ち品を狙う賢さ
少しでも安く購入したいなら、セール時期や型落ち品を狙うのも有効です。
- セール時期:
- 年末年始セール、夏休みセールなど、一般的なセール時期。
- 大会シーズン後などに、専門店が独自のセールを行うこともあります。
- クラブ経由で割引購入できる場合もあります。
- 型落ち品:
- 新しいモデルが発売されると、旧モデルが割引価格で販売されることがあります。特にユニフォーム類などは、機能的に大きな差がない場合も多いです。
- 情報収集:
- フェンシング専門店のウェブサイトやSNSを定期的にチェックしましょう。
- クラブのコーチや先輩保護者からセール情報を教えてもらえることもあります。
すぐに必要でないもの(予備の剣など)は、セール時期まで待って購入するのも賢い方法です。
節約術⑤:焦らない!最初は最低限の用具からスタート
「やる気満々の子供のために、最初から全部最高のものを揃えてあげたい!」という気持ちも分かりますが、焦りは禁物です。
- 体験入会や見学を活用: まずは体験や見学で、子供が本当に興味を持つか、続けられそうかを確認しましょう。クラブによっては、体験時には用具を貸してくれる場合もあります。
- クラブで借りられるものを確認: クラブによっては、最初の数回は剣やマスクを貸してくれる場合や、共用の用具がある場合があります。
- 必要最低限から揃える: 最初は、安全上必須のマスク、ジャケット、プラストロン、グローブ、パンツあたりから揃え、電気系のコードなどは必要になってから買い足す、という方法も考えられます(クラブの方針によります)。シューズも、最初は体育館シューズで代用できるか確認しましょう。
子供の興味が確かなものになってから、徐々に用具を揃えていくというスタンスも、無駄な出費を防ぐためには重要です。
失敗しないための用具選びの注意点
節約も大切ですが、安全に関わる用具選びで失敗はしたくありません。以下の点に注意しましょう。
- 【最重要】安全性:安全基準を確認する
- フェンシングの用具には、国際フェンシング連盟(FIE)が定める安全基準があります。特にマスクやユニフォーム(ジャケット、パンツ、プラストロン)には、規定の強度(ニュートン(N)数)が定められています。
- 国内の多くの大会ではFIE公認である必要はありませんが、安全性の高いものを選ぶに越したことはありません。特に国際大会を目指すレベルになるとFIE公認用具が必須になります。
- 購入時には、FIEマークや国内の安全基準を満たしているかを確認しましょう。不明な場合は、必ずコーチや専門店に相談してください。中古品の場合は特に注意が必要です。
- サイズ:必ず試着を!
- 用具は必ず子供の体に合ったサイズを選びましょう。大きすぎると動きにくく、小さすぎると窮屈で危険な場合もあります。
- 特にマスクやジャケット、パンツ、グローブはフィット感が重要です。可能であれば必ず試着しましょう。オンラインで購入する場合も、サイズ交換が可能かなどを確認しておくと安心です。
- 成長期なので少し大きめを選びたい気持ちも分かりますが、あまりにブカブカなものは避けましょう。袖や裾の調整が可能かなども確認ポイントです。
- 専門家への相談:コーチや専門店スタッフに聞く
- どのメーカーが良いのか、どのレベルの用具を選べば良いのかなど、分からないことは遠慮なくクラブのコーチやフェンシング専門店のスタッフに相談しましょう。経験に基づいた的確なアドバイスをもらえます。
まとめ:工夫次第でフェンシングは始められる!
フェンシングの初期費用は、確かに安くはありません。今回ご紹介した相場を見ると、約7万円から16万円程度が一つの目安となります。
しかし、諦める必要はありません!
今回ご紹介した5つの節約術、
- 中古品・お下がりの活用
- レンタル制度の利用
- 初心者向けセット商品の検討
- セール・型落ち品の活用
- 最低限の用具からスタート
これらを上手く組み合わせることで、初期費用を大幅に抑えることが可能です。
大切なのは、情報収集と比較検討です。そして、節約ばかりに目を向けるのではなく、お子様の安全を第一に考え、体に合った適切な用具を選ぶことです。
フェンシングは、お子様の身体能力だけでなく、集中力、思考力、精神力、そして礼儀作法まで、多くのことを学べる素晴らしいスポーツです。費用面でのハードルを少しでも下げ、一人でも多くのお子様がフェンシングの世界に飛び込めるよう、この記事がその一助となれば幸いです。
さあ、情報収集を始めて、お子様と一緒にフェンシングの世界への扉を開けてみませんか?




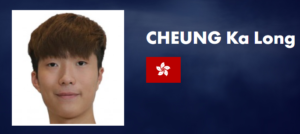


コメント